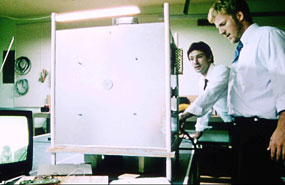|
|||||||||
|
映画が判らなくて、2回も映画館に行ってしまった。 上映前の夕食にお酒を飲んだら、映画の冒頭でちょっとウトウトしてしまった。 それも手伝って、この映画が何を訴えているのか、理解できなかった。 「ロスト ハイウエイ」や「メメント」「π(パイ)」など、難しい映画は今までもあった。 しかし、理解できないことは初めてで、再度、同じ映画を見に行かざるを得なかった。
2004年のサンダンスで、審査員大賞と科学技術関連映画賞を受賞したとあった。 そのため、新規な映画だとは判ったが、何を主題にしているのか、1度見ただけでは当方には理解できなかった。 単家族論や母殺しで、時代の最先端を切り開いてきたと自惚れていたが、とうとう時代に追い越されたかと、落胆することしきりであった。 それにしても、こんな難解な映画に、審査員大賞を与えるサンダンスは、何という映画祭だ。 2度目に見に行ったら、無限の自己相対化が主題だと判った。 鋭い指摘だとは理解するが、もう少し判りやすくしてほしかった、というのが愚かな観客の希望である。 お金がない中で作られているのもよく分かる。 ビデオで撮ったものを、劇場用のフィルムに変換したのか、画面が飛んでいる部分が多く、画面も見にくい。 と、文句を付けたくなるが、とにかく1度では判らなかった映画である。 タイムマシンを使った映画は、今までもたくさんあった。 しかし、この映画の優れていることは、タイムマシンを使うことが、無限の自己相対化を生み、自己の無限の増殖を生み出す、と主張していることだ。 前近代の笑いは、バナナの皮に滑って転ぶ人を笑うものだが、近代の笑いは、バナナの皮に滑って転ぶ人を笑う自分を笑うものだ。 科学は自己とは別の、事実としての世界があることを教えた。 そのため近代人は、自己を相対的に見る目を獲得した。 自己相対化の眼こそ、近代人を近代人たらしめている。 しかし、自己相対化は認識の基盤を消失させる、という射程をももっている。 アーロンとエイブを喧嘩させたりしているので、この映画は無限の自己相対化を描くに止まり、近代批判までは意図していないだろう。 ひょっとすると、時間移動での矛盾だけを描いたのかも知れない。 しかし、監督の意図を越えて、この映画は鋭い近代批判になっている。 自己相対化したがゆえに、自己と事実が分離し、科学が発展し得たのだが、科学的認識は認識する人間の存立基盤を保証しない。 前近代人は、神に信の基盤を置いたからだけではなく、自己と現実を一致させていたので、実感が現実に立脚し、自己認識は現実に基盤をおいていた。 そのため、前近代人は確固たる自己を確立し得たし、堂々とした人生を歩むことが出来た。 それに対して、近代人は自己相対化によって、常に自己を疑うがゆえに、確たる自己を確立できない。 近代人の自己は、つねに揺れ動く状態でしかない。 前近代人は鏡に映る自己を見ていた。 1枚の鏡を見ているだけでは、自己相対化はおきない。 近代人は、鏡を2枚向かい合わせる。 1枚では1面だった世界が、2枚合わせることによって、無限の世界を創り出す。 ここで、自己相対化が無限になる。この映画では、タイムマシンのなかへ、タイムマシンを持ち込んで、2重の時間移動をする。 そのため、無数の自己が生じてしまう。 その分身が分身を生む矛盾が、徐々に拡大し、とうとう収拾がつかなくなってしまう。 分身と自己の遭遇は禁止されていることなど、タイムトラベルのルールを踏襲しているが、タイムマシンのなかへタイムマシンを持ち込むことは実に新しい。 これによって、無数の分身が生じてしまう。 これは無限の自己相対化が、必然的にもたらす論理の破綻である。 この映画は、自己相対化を自己相対化させることによって、無限の自己相対化を生じさせ、結局は自己そのものが破綻していく過程を描く。 近代の認識だった自己相対化は、自己相対化させることによって、無数の自己が生じて自己が崩壊する。 近代人の自我は、まったくこの映画が描くとおりである。 結局、近代の自己相対化は認識の基盤を失って、論理必然的に崩壊せざるを得ない。 物語の展開は、タイムマシンは2人だけの秘密だったが、分身たちの登場によって、2人だけの秘密ではなくなっていく。 ここでどこまでが自己で、分身だか判らなくなる。 自己と分身の往復する構造が、まったく同じ俳優によって演じられているので、自己と分身の区別が不明瞭で非常に理解しにくい。 今登場しているのは、本当の自己か分身か区別が付きにくい。 結局のところは、自己でも分身でもなく、どちらも自己でありかつ分身でもある。 デジタルの世界では、コピーという概念が成立しない。 当初、本物の自己だったアーロンにしてもエイブにしても、当初は自己が分身を分身と呼んでいるが、じつは分身も自己とまったく変わりない。 デジタルの世界ではオリジナルとコピーは、まったく同じである。 それと同じように、別の次元にいるアーロンやエイブは、すべて本物でありかつコピーなのだ。 人間のコピーも本物と同じだということが、なかなか理解できないから混乱する。 自己と分身は、いずれも意志を持っている。 しかもその意識は別々のものであり、相互に連関はない。 電波は時間を超えるので、友人の誰かがアーロンに電話をかけると、どのアーロンが電話をとっているか判らない。 しかも、自己と分身の接触は禁止されているので、アーロン同士は連絡が取れない。 分身が何人登場しようと、アーロンは本来は1つであり、アーロンの認識がまちまちであることはあり得ない。 にもかかわらず、意志を持つ分身は勝手に行動し、とうとうアーロンは人格の統一がとれなくなる。 だから、人格の分裂に耐えられなくなったアーロンは、最後に国外へと脱出しなければならなくなったのだ。 しかし、これをちょっと先に進めれば、根底的な近代批判になる。 無限の自己相対化が、人格の分裂をよび、人格の統一が維持できないことになる。 人間は唯一の存在であるという、近代の大前提が否定されざるをえない。 これは近代社会が維持できないことだ。 自己相対化が社会を滅ぼす。 監督は意図しなかったかも知れないが、これがこの映画の主題がもつ射程である。 科学技術の進歩が、人類を滅ぼすいう映画はあった。 しかし、近代人の論理そのものが、崩壊を必然としているという映画は初めてであろう。 タイムマシンは論理的に不可能だろうが、認識構造が崩壊を不可避としているというのは、実に説得的である。 きわめて哲学的な映画であり、サンダンスで物議を醸すのは当然であろう。 初監督作品で、低予算映画だからやむを得ないとはいえ、映画としては未完成な部分が多い。 どんな難しい主題でも、判りやすくは出来るし、より多くの人に見て欲しいがゆえに、判りやすく作るべきだと思う。 新たな地平を見せた映画には、星を献上するこのサイトとしては、星を献上せざるを得ないので星を献上しはする。 この映画でスポンサーが殺到するだろうから、今後もう一度作り直して欲しい。 「マクマレン兄弟」のエドワード・バーンズ監督のように、初作品で秀作をものにしながら、監督として自滅してしまう人もいる。 思考者としての力量は判ったが、映画監督としての表現力を付けて欲しい。 次作目まで仮の星としておきたい。 2004年アメリカ映画 (2005.10.2) |
|||||||||
|
<TAKUMI シネマ>のおすすめ映画 2009年−私の中のあなた、フロスト/ニクソン 2008年−ダーク ナイト、バンテージ・ポイント 2007年−告発のとき、それでもボクはやってない 2006年−家族の誕生、V フォー・ヴァンデッタ 2005年−シリアナ 2004年−アイ、 ロボット、ヴェラ・ドレイク、ミリオンダラー ベイビィ 2003年−オールド・ボーイ、16歳の合衆国 2002年−エデンより彼方に、シカゴ、しあわせな孤独、ホワイト オランダー、フォーン・ブース、 マイノリティ リポート 2001年−ゴースト ワールド、少林サッカー 2000年−アメリカン サイコ、鬼が来た!、ガールファイト、クイルズ 1999年−アメリカン ビューティ、暗い日曜日、ツインフォールズアイダホ、ファイト クラブ、 マトリックス、マルコヴィッチの穴 1998年−イフ オンリー、イースト・ウエスト、ザ トゥルーマン ショー、ハピネス 1997年−オープン ユア アイズ、グッド ウィル ハンティング、クワトロ ディアス、 チェイシング エイミー、フェイク、ヘンリー・フール、ラリー フリント 1996年−この森で、天使はバスを降りた、ジャック、バードケージ、もののけ姫 1995年以前−ゲット ショーティ、シャイン、セヴン、トントンの夏休み、ミュート ウィットネス、 リーヴィング ラスヴェガス |
|||||||||
|
|